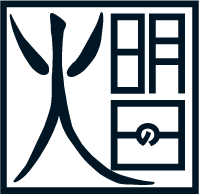2022年1月18日
「公衆浴場と公衆食堂」
藤原辰史(歴史学者)
学生だった四年間、私は京都左京区北白川の安下宿に住んでいた。台所とトイレは共用で、風呂はなかった。そこで、下宿から自転車で2分、歩いて5分の銭湯に通った。真冬も真夏も雨の日も通った高原温泉という名の銭湯は、今はもうない。
銭湯は面白い場所だった。番頭のおかみさんがいることを全く意識せずに服を脱ぎ捨て、棚に入れて鍵をし、鏡で筋肉をムキムキにしてポーズを決める学生を横目で見ながら、洗面器に入れたシャンプーとリンスとボディソープと垢すりを持って風呂場に入る。真っ白な湯気に覆われたタイル張りの空間で、体を洗って、シャワーで流し、ほどほどにぬるい薬風呂に入り、つぎに皮膚が真っ赤になるほど熱い湯船に浸かる。疲れている時は最初にサウナにも入る。真夏には、サウナのあとに水風呂に入る。
銭湯が不思議なのは、みんな裸なのに公共空間である、ということだ。裸のおじいさんが二人、世間話に興じている。筋肉ムキムキのスポーツマンの二人が仲良く湯船に浸かって、今日の練習について話している。男湯と女湯の壁を挟んで夫婦が喧嘩のように叫びながら会話している。男湯も女湯も眺められる高い位置にテレビが設置されていて、いつも野球の実況中継が流れていて、そこではいつも阪神が戦っており、おじさんたちが投手や野手にやや辛めの評論を加えている。優勝がかかっていていたときは大盛り上がりだった。均衡した試合で阪神の選手がしくじると、みんなでため息を漏らすこともあった(私も阪神ファンである)。湯気とほてった体は会話を促進するみたいだ。私も大学でソフトテニス部に入っていたが、仲間と銭湯に入って練習の疲れをほぐすと、自然と会話がはずむ。
会話だけではない。そこには新聞や週刊誌や漫画雑誌が置いてある。おかげで、漫画や雑誌はあまり買わないで済んだ。大袈裟にいえば、街の情報ステーションでもある。
今月の生活費に余裕があるときは私は飲みものを買った。番頭に行って、コーヒー牛乳を買う。これがまたおいしい。
もう一つ興味深いのは、服に着替えてからはあまり長居しないことだ。全裸か半裸の人はいくらでもゆっくりできるが、服を着込んだ瞬間になんだか居心地が悪くなる。現在住んでいるところの近くにある銭湯は脱衣所とは別に待合室のような場所があって、男女がそこで落ちあうことができるので、服を着て雑誌をめくりながら、しばらく過ごせる。ただ、お風呂入ったあとのだらっとした格好でこのままこの場所で食事したり、ビールを飲んだりできたらいいのにな、と思ったこともしばしばあった。いまではスーパー銭湯がそうかもしれないが、あれはちょっと大きすぎる。
拙著『縁食論』(ミシマ社)で、公衆浴場のような食堂の可能性について論じた背景のひとつには、以上のような学生時代の銭湯の記憶があったのだと思う。とくにべったり付き合わなくても、服さえ脱いでいればゆったりいさせてくれる場所。客の回転を考えなくてもいい場所で、ご飯を食べたり、飲みものを飲んだり、ぼんやりとテレビを見たり、お話をしたり、漫画を読んだりしてくつろげる公共空間。狭い下宿に帰ってくると、ほんのり寂しさがつのるけれど、明日もがんばろか、と思うことができる、そういう空間が、くつろぐことがますます自宅だけに押し込められている今、必要とされていると思う。