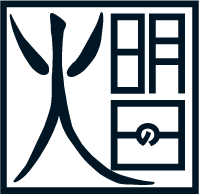2021年1月8日
食の非人間中心主義的考察
藤原辰史(歴史学者)
フード・ジャーナリストのマイケル・ポーランは、『雑食動物のジレンマ』の冒頭で、食品産業の発展はかえって食の選択を難しくしたと述べている。現代社会では、あまりにも食の選択肢が多すぎて、毎日の食事の決定を毎日膨大に目にする広告に左右されてしまうからである。この食の主体性の喪失状態を突破するために、ポーランはイノシシを撃ってさばき、山でキノコを集め、原初的な食のあり方を求め、野生を回復していく。
ただ私は、食の受動性を乗り越えるためには、その受動性を一度徹底してみる、という方法もあると考えている。動植物の死骸のかたまりを熱や刃で変成させたものを口の中に入れて、歯で食いちぎり、舌で舐めずり、飲み込む行為のことを、私たちは「食べる」という動詞で表現している。しかし、このような行為を「私は食べる」と表現することで、人間は何か肝心なことを見落としてきたのではないだろうか。
第一に、食べる主体は人間だけではない。もしも食べものが味噌や醤油やヨーグルトやチーズであるならば、それはすでに無数の微生物による発酵がなされている。つまり、微生物が食いちらかし、さまざまな風味をまとった動植物の死骸を私たちは食べているのだから、微生物と一緒に食べていると言える。たとえ発酵食品でなくても、料理人の手に存在していた微生物は食べものにくっついて私たちの内臓に入ってくるし、大腸にも十兆を超えると言われる微生物たちがそれらを待ち構え、人間の消化機能から免れた食べものを食い荒らすのである。
第二に、私たちは微生物と一緒に「食べる」だけではなく、食べさせられている、と見ることはできないだろうか。たとえば繊維質の入った焼き芋が食べたくなるとき、それは私の欲望だろうか、それとも繊維質を食べる腸内の微生物の欲望だろうか。あるいは、もっと突き放して食べる行為を考えてみれば、人間は、口から取り入れ肛門から別の生物たちにとっての食べものを生み出す生態系の通路にすぎない。私たちは、身体を貫く食物連鎖の流れに、ただ自分の身体をあわせているだけではないだろうか。
以上のような思考は、食べる行為を人間中心主義的に語ることの傲慢を私たちに教えてくれる。食べる行為は、農業や漁業や料理の担い手という他人の行為に依存しているように、そもそも他力本願な行為であるのだが、その「他力」もまた単に人間の力だけを示すわけではない。この他力本願の究極を突き詰めていくと、グルメ番組や広告に今晩の夕食を選ばされている私たちは、それだけではまだ受動性が足りない、とさえ言えるのではないか。そして、一度、徹底して自己の存在を主語から解き放ち、目的語に置き続けることは、単に食の問題にとどまることのない思考のほぐしをもたらすと私は思う。