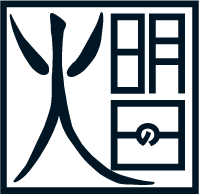2021年10月1日
「発酵の人文学的意義」
藤原辰史(歴史学者)
納豆、味噌、醤油、日本酒、漬物、ヨーグルト、チーズ、ワイン、パン。洋の東西を問わず、私は発酵食が好きでたまらない。納豆やチーズのあの香りは、腐敗臭にも近い香りだが、病みつきになる。日本で最もにおいが強い発酵食のひとつで、滋賀県の名産物である鮒寿司も、日本酒と一緒に食べるとなんとも言えない幸福感に浸れる。発酵食は、どこか体のにおいにも近く、不思議な懐かしさも感じ、同じ食材でも地域によって全く異なる。また、藍染めも藍を発酵させなければ、あのような色合いも香りも生まれない。発酵文化は人類がこの世に送り出した最高の芸術だ、と叫びたくなる衝動に駆られることもある。
そればかりではない。私は、発酵文化は、人文学的な観点からしても、とても大きな意義を持っていると考える。
第一に、「待つ」ということの重みを伝えてくれること。私たちはつい、世界で起こるさまざまな現象を、歴史的および地理的経緯を無視して、現在の有様としてとらえがちである。しかし、ふくよかな香りと旨みを引き出すためには、一ヶ月でも一年でも同じ場所でじっと待つことを宿命づけられている発酵食は、そのような短絡的な見方が薄っぺらいことを我々に教えてくれる。何かを決めつける前にじっくり考える行為も、何かの現象を歴史から掘り起こす行為も、人文学の営みの基本だが、これは発酵文化の基本と通じるものがある。
第二に、思考を「寝かせる」ことのの意味を伝えてくれること。高度情報化社会の中で、私たちはつい、ネット上の情報を読んだ瞬間にそのことについて知ったつもりになりがちである。しかし、そうして頭に入ってきたデータの寿命は、本を読んでじっくり頭に染み込んだ知識の寿命よりも短い。本で読んだり、人から聞いたことを、何日も頭の中において、睡眠を何回も挟むことで、その情報は私たちの生活に根ざした知恵、あるいは、柔軟な知へと変化していく。ちょうど、発酵するあいだに微生物の力によって味わいが静かに深まっていくように。 第三に、副産物というあり方の面白みを伝えてくれること。なんでもかんでも「生産」するように圧力を受ける社会の中で、私たちは「生産」に疲れてきている。しかし、アルコールにせよ、うまみ成分にせよ、発酵過程で生じるものは、植物や動物が微生物によって分解されていく過程の副産物に過ぎない。たまたま、分解中に生じたものを、人間にとって美味しいから、という理由で横取りしているに過ぎない。私たちは、主産物を重視しすぎて、何かを作るときや壊すときの副産物に対し、注意を払うことを怠ってきたかもしれない、と、納豆や日本酒を愉しむときにふと思うことがある。
待つこと、寝かせること、そして、副産物を愉しむこと。発酵文化が私たちに教えてくれるどれもが、近代社会によって弱体化してきたものばかりである。発酵のかわりに、待たなくてもよい化学製品の調合が重宝されることで、失われてきたものばかりである。人文学は、そのような失われてきたものを拾い、いまある世界が唯一の世界ではないことを伝えることが課題であるとするならば、発酵文化の奥深さから学ぶことはとても多いと思う。