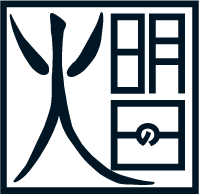宮ティーハウス|版築ワークショップ
TOMORROWが推進するプロジェクト「あしたの畑」では、これからの食と暮らしに着目し、ユネスコでの持続可能な建築学教授に任命されている陶芸作家マーティン・ローチと建築家アンナ・ヘリンガー、 TOMORROWの共同制作による自然と共存する半屋外のアートインスタレーション「宮ティーハウス」の制作を計画しています。
5年目を迎える今年は、5つ目の展示空間となる「宮ティーハウス」を地域の土を使い、ワークショップ形式で1から手作りで完成させることを目指し、あたらしい“食とアートの場”をつくります。
ワークショップに参加していただくことで、地域の素材や伝統的な建築技術であり、地球に戻る土の建築ー版築を学び、地域社会や環境と調和するこれからの現代的な建築のあり方を考えるきっかけとなれば幸いです。
ワークショップ開催地
京都府京丹後市丹後町宮
宮のあしたの畑
丹後半島-円には神話や伝承が数多く残ります。「間人(たいざ)」の地名は、聖徳太子の生母である間人(はしひと)皇后が、蘇我・物部の戦を避けてこの地に逃れ、後に大和に戻られたので「退座」と呼ばれるようになったという伝承があり、この地域には聖徳太子の異母弟である麻呂子王の三鬼の退治にまつわる話も伝わっています。
丹後には日本海三大古墳をはじめ、数多くの古墳が残ります。古代の人々は土を盛り、築き、そこで集い、語らい、祈りを形にしてきました。墳丘長190mで日本海側最大級の前方後円墳である「神明山古墳」の麓に位置する今回の開催地が「宮のあしたの畑」です。
宮のあしたの畑には、西沢立衛建築設計事務所設計の最小建築である「納屋」やアーティストのテレジータ・フェルナンデスと木工作家の中川周士、TOMORROWの若い世代によるコラボレーション作品「Field of Stars」が展示されています。


Darko Todorovic/ vai Vorarlberger Architektur Institut
共同クリエイター
マーティン・ローチ
マーティン・ローチと彼が代表をつとめるLehm Ton Erdeは、過去35年にわたり、世界中で版築技術を活用して数多くのプロジェクトを実現してきました。様々なものが工業化されたヨーロッパにおいて、土という原始的な素材を、現代的で持続可能な製品として確立しています。版築のユニット化を実現した革新性により、ユネスコでの持続可能な建築学教授に任命され、国際的な評価を得ています。
アンナ・へリンガー
アンナ・へリンガーは、持続可能な建築、特に版築など土を用いる革新的なアプローチで知られる建築家です。地元の素材と技術を深く尊重するとともに、地域への関与と取り組みを特徴とし、ユネスコでの持続可能な建築学教授に任命されました。ガーナやバングラディッシュにおいて、地域の人々と共同で学校などを作る活動を行っています。
参照
今回のプロジェクトに関するマーティンとアンナへのインタビューはこちら
2024年9月に京都大学で開催したアンナと平田晃久氏の対談のレポートはこちら
スケジュール
・説明会
A) 8月25日(月)13:00-14:00
B) 9月 7日(日)17:00-18:00(zoomでの開催)
・日 程
第1期:10月21日~23日
第2期:11月2日~8日
第3期:11月22日~30日
9時 作業開始
17時 作業終了
途中休憩3回(昼休み含む)
・マーティン・ローチ、アンナ・へリンガー、左官職人による版築指導
11月2日(日)、3日(月・祝)
定員:10人、先着順。
参加希望者は、下記の参加条件を確認の上、条件を満たす方のみメールにてご連絡ください。
作業内容
・突き棒やハンマーなどで土を突き固めて版築の壁を作る。
・土と砂利を配合して材料を作る。
・型枠の準備、組み立て、解体。
・周囲の植栽の準備(整地、植樹)。
服装等
水に濡れたり汚れても良いシャツ・ズボン・帽子、タオル、軍手、動きやすい靴、飲料水をご準備の上、参加ください。
過去の版築ワークショップの様子
参加条件
・期間中3日以上参加していただける方。
・参加費は必要ありません。
・現地までの交通費、宿泊費、現地での生活費と交通費は参加者の自己負担となります。
・宿泊場所の紹介をします(1泊素泊まり5,500円~、ご自身でご予約をお願いします。)
・8月25日(月)または9月7日(日)に開催するオンライン説明会にご参加ください。
・中学生と高校生の参加者は、保護者の同意が必要です。
参加方法
メール(info@tomorrow-jp.org)にて、9月6日(土)までに下記の情報をご連絡ください。
・氏名
・年齢(中学生~)
・性別
・職業
・住所
・参加希望期間
・参加動機
・説明会参加希望日