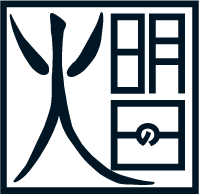2025年7月22日
あしたを耕す者たち
第5回
マーティン・ローチ(陶芸家、ユネスコ持続可能な建築学教授)
アンナ・ヘリンガー(建築家、ユネスコ持続可能な建築学教授)
徳田佳世(キュレーター)
いのちの輪を循環させること
「自分の家を建てる」と言って、自分の手でノコギリとカナヅチを握りしめる人は何人いるのだろう。食べて、寝て、大切な人と時間を過ごす、生活の基盤である家のつくり方を、しかし、知っている人は少ない。NPO法人TOMORROW の代表である徳田佳世さんが陶芸家であるマーティン・ローチさんと建築家アンナ・ヘリンガーさんに相談を持ち掛けたのは、その「家を建てる」という技術を手の内に取り戻すことが、現代人が今の世界を生き、未来を描くために必要だと感じたからだ。
彼女の呼びかけに応え、マーティンとアンナの先導のもと京丹後市丹後町宮地区で地域コミュニティを巻き込んだ土のインスタレーションが展開しつつある。
素材へ敬意を
まずは、マーティンに、土との出合いについて伺いたいと思います。
マーティン・ローチ(M):私の育った環境はとてもクリエイティブで、自然と陶芸や彫刻に親しむようになりました。当時の私にとっては、土という素材自体が魅力的で、それ自体が芸術だと感じていたんです。
40年ほど前に大きな変化が訪れました。粘土を焼成するのにかかるエネルギーの膨大さに、気づいてしまったのです。そこで、焼き締めていない、つまり乾かし固めただけの土を使って彫刻を作る実験を始めました。そうすると、雨水からしっかりと保護されていれば、土の構造は十分に強固であることが分かりました。
そこからは少しずつ規模が大きくなっていったので、素材をより効率的に扱うための道具やシステムの開発を始めました。そうして、現代に適した版築法にたどり着いたのです。
土を突き固めて建材として使う版築法は古代から存在すると聞きました。古の英知から学ぶことで革新的な作品が生まれているのですね。
M:始めた当初は、版築技法の知識は無かったので、ただ土を乾かして彫刻を作っていただけです。16歳で訪れたアフリカで、土が建築に使用されている様子を目にしました。さらに、版築はヨーロッパでも何世紀にもわたって存在していたことを知ったのです。今も土壁で作られた家屋が残っている地域もあります。
私にとっては、まず素材としての土がとても魅力的なんです。この至ってシンプルな素材は、世界中のどこにでもありますが、かといって、まったく同じ土は2つとしてありません。この素材を理解するには、その奥深さをまず理解しなくてはなりません。
土はまるで抽象芸術みたいだな、と思うことがあるんです。一見単純そうに見えて、実はその奥に読み解くべき情報がたくさん潜んでいるなんて、まさにそうですよね?
あえて課題を挙げるとしたら、この土という素材は、誰でも簡単に手に入れることができるものの、現代の建築システムからは疎外されていることです。建築材料としては、もはやほぼ馴染みのないものとなっていますし、先入観もある。まずはそこを克服しなければなりません。
アンナ・ヘリンガー(A):建築材料としての土を堅固かつ美しい素材として知らしめたのは、マーティンが初めてではないでしょうか?もともと、土は安価で、耐火性があり、安全だったので、古くから建築材料として使用されてはいたのです。でも、最終的には、石や漆喰で覆われて、土という素材が表に出ることはなかったのです。マーティンは、土の表面をあえて残し、デザインとして見せることで、その素材としての美しさを強調したのです。つまり、土という素材の尊厳を取り戻したのです。

宮ティーハウスの模型
徳田さんは、マーティンとアンナの作品のどこに惹かれたのでしょうか?
徳田佳世(K):ここに至るまでに携わっていた二つのプロジェクト(豊島美術館と地中美術館の建設)は、コンクリートをたくさん使って作られた建築物でした。その二つを完了させた後に、次の方向性を模索し始めていたんです。残りの人生をかけて追求したい仕事はなんだろう、と。
同時に、職人たちとの仕事を始めてもいて、手でものをつくる、という考えに惹かれていたんですよね。その方向を深めていた時に、日本の雑誌でアンナの仕事を紹介する記事を読んで、「これだ!」と思いました。
あしたの畑を、若者が家を建てることを学ぶ機会にできないかな?と考えたんです。現在の日本の義務教育では、自分の家を建てる方法は教えてくれません。どんなに安全かつ安価で持続可能な材料を使うのであっても。
あしたの畑でつくるものは、地元の人にとって「いつの間にかそこにできていた建築物」にはしたくなくて。それだったら、私が若い世代も参加できる教育の場を作るしかない、と思ったのです。私自身の勝手な熱意と言ってしまえばそれまでですけど…。そこで、アンナに連絡を取ったんです。
A:マーティンも全く同じ考え方。変化を望むなら、まず自分がその変化になりなさい、っていうことね。
素朴な素材を大切にする国
徳田さんが連絡をくれた時、どう思いましたか?
A:本当に嬉しかったです。日本は、建築を学んでいた時に初めて訪れて、とても感動した思い出があったので。その時訪れたのは桂離宮で、天皇が住まう空間に、最も素朴な素材である土が使われていることに驚かされました。「私達は、農民・庶民と同じ素材を使います。」という意思の表れだと私には感じられたのです。「ただし、その素材には最上級の技術、職人技、細心の注意を払います。」と。価値は素材そのものにあるのではなく、それを高める人間の技術にある、という美しく、驚くべきメッセージでした。
さらに、桂離宮が建てられたのは、ヨーロッパではバロック期だったと気づいてはっとしました。大理石や金など、最高級素材を集めた豪華絢爛な建築物の最盛期でした。歴史を振り返っても、世界中の皇帝や王族、エリート層は、珍しい素材を異国の地から取り寄せて、富と権力の象徴としてきました。現在もそうですよね。成功者は、成功の証として希少価値のある高級素材を求めがちです。
私はバングラデシュで携わった仕事にも、日本で得た教訓を大切に生かしています。農民のための建物でも、公立学校でも、素材は同じものを使ったんです。ただ、その素材に注ぎ込む職人技や洗練度が変化しました。
つまり、一部の人しか手に入れることのできないものを見せつけるのではなく、全員の手が届く素材で何ができるかを追求して明らかにしたのです。例えば竹や粘土といったどこにでもある素材を活かして、美しくて、長持ちする建築物をつくることができる。それは誰もが作れて、方法も簡単に真似できて、そして誇りに思うことのできる建物なんです。

Anandaloy oustide photo: Kurt Hoerbst
共有される材料と知識
もう少し詳しく教えていただけますか?
A:マーティンもよく言うように、土を使った建物は、比較的簡単につくれるんです。方法を分かっている人が 1 人か 2 人いれば、あとは経験のない多くの人々に手伝ってもらってできる。あるプロジェクトでは、子どもたちにも参加してもらいました。
制作過程においては、誰もが仕事を見つけて、何らかのかたちで貢献できるんです。建築は、一人ではできないので、常に大勢の協力が必要です。力仕事をする人にお茶を淹れたり、スープを作ったりといった小さな貢献も、みんなでする作業の大切な一部です。そうやってなるべくたくさんの人に参加してもらうことで、自然と共同体の意識が生まれます。
それが大切だと思うので、何かの建築に携わる時には、その過程で自然とつながりが育まれるような仕組みをデザインするようにしています。単に構造物を造ることだけが目的ではないのです。だって、今の社会に足りないのは物質的なものではないですよね?私たちが求めているのは、つまるところ共有できる経験であり、目的意識であり、人とのつながりなんです。
このインスタレーションは「Tea House」という名前ですね。日本語で言ったら「茶屋」といったイメージでしょうか?この名前の由来を教えてください。
K:マーティンとアンナに会いにシュリンス(オーストリア)を訪ねたことがあったんです。マーティンが育った村で、彼が自分で建てた家で、地元の野菜を使ったスープをごちそうになりました。それはとても豊かな気持ちにさせてくれました。私たちがつくりあげる場所も、その土地に深く根ざし、訪れる人に開かれていて、心と体に栄養を与えるような空間であってほしいと思います。
食は生活の中心ですよね。私たちが健康でいられるのも、健康的な思考を保つことができるのも、全て口に入れるもののおかげだと思うのです。だからこそ、食事と、食事を共にする経験が生活の中心にあることを表す名前が良いな、と思って。Tea Houseにたどり着いたんです。
誰しも身の回りにある景色に影響を受けますよね。毎日眺めながら育つものだし、いつのまにか浸み込んでいるものだと思うんです。だからこそ、子どもたちの周りにある景色は重要な意味を持つと思っていて。間人で私たちが取り組んでいる景観が、いつか子どもたちや若者たちに、地域の未来について考えるきっかけとなれば嬉しいですね。

Model for MIYA Tea House, Anna Heringer, Martin Rauch & TOMORROW, 2025
包み込む円
そのコンセプトに基づいて、実際の設計はどのように進んだのでしょうか?
A:最初は苦労しました(笑)。何パターン考えたか思い出せない程です。「いけるかな?」と思えるものも、何かが足りなくて。「どこにでもありそうだな」と思えてしまったんです。現場に戻り、問い直しました。「ここでなければならないもの。日本ならではのものは?」と。
現実問題として、地震は無視できない課題でした。土の構造物に対して挙げられる反対意見のひとつでもあります。そこで、地震が起こり得る土地で最も安全な形は?と考えました。そしてたどり着いたのが円形なんです。
M:円形は揺れに対して非常に有効です。特に木材と組み合わせると、自然な安定性を発揮します。私たちは伝統的な建築手法を参考にし、それを現代に応用しました。
A:その後に分かったんですけど、あしたの畑には、円形の木造構造物を専門とする職人がいるんです。とてもラッキーだと思いました。円形という特殊なインスタレーションを実現するには、そのつくり方に精通した職人が必要で、どこにでもいるわけではないのです。その人材がいると分かり、円形であることの意味はさらに深まりました。
円は、「コミュニティ」も象徴しています。人々が集まり、つながりを感じることができる空間は間人でも求められているはずです。これも大切なコンセプトの一部になりました。
結果として、非常にシンプルな円形にたどり着いたわけなのですが、実際の環境はただの円形にとどまりません。火を焚くことができて、水の汲める井戸があって、薬草を植えることのできる庭もあって。そこには小さな生態系が凝縮しているんです。庭は、お年寄りがしゃがまなくても手が届くように少し高さを出しています。水やりに時々様子を見に来て、地元の人と出会っておしゃべりが始まるかもしれないですよね。その様子を思い浮かべると、どこか心が癒されます。
前回のインタビューで、徳田さんは、詩人、科学者、哲学者など、あらゆる分野の人々が集まり、世界について語り合う場をつくりたいと語っていました。それが実現しつつあるのは、とても素晴らしいことです。
K:マーティンとアンナがいなければ、これはまだアイデアのままでした。彼らがそれを実現してくれたのです。
A:カヨの考え方がとても好きです。派手なものをぱーっとつくろう、ではなくて、「すでにそこにあるものに注目し、その良さを引き出す」という哲学は、非常に力強いと思います。

マーティンとアンナ 宮のあしたの畑にて
アンナさん、あなたの専門分野である「再生可能な建築」とはどのようなものですか?
A:私にとって再生可能な建築とは、循環、つまりいのちの循環のことです。それは単に新しい創造を意味するものではなく、衰えや、死さえも内包します——それが重要なんです。多くの文化において、自然と調和した建築を妨げる最大の要因の一つは、この「衰え」に対する恐れ、死への恐怖です。それは古代から存在している感情ですが、今でも根強く存在します。でも、本当に自然と調和しようと思ったら、いずれ衰えていくこと、それが過程の一部であることを受け入れなければなりません。
昔は、今ほど完璧主義ではなかったですよね。シワや老化は、人生の一部として受け入れられ、そこには尊厳や美さえありました。同じように、古いものはその経年変化も含め、長らく使われてきた記憶の跡を宿すものとして私たちは大切にしてきたはずです。
私にとって再生可能な建築とは、その場所のもつ可能性を尊重することです。必要以上に取らないこと。私たちが作るものが、やがてその起源である大地に戻れるように建てること。だって、何も永遠に続くものはないのです。いずれすべては風化します。
大切なのは、建物物がどれだけ持つかではなく、その制作過程を通じてどれだけの知識が生まれ、共有されたかなのです。特に、自然素材を丁寧かつ創造的に扱うための知識と技術は継承されるべきです。

バングラデシュでの取り組みを紹介するアンナ(京都大学にて)
現代の多くの高層建築物は、知識ある専門家によって設計され、鋼鉄、コンクリート、ガラスなど、極めて耐久性の高い材料を使って建てられますが、その建築に関わる知識は専門家の中に留まり、庶民の間で共有されません。その結果、いずれコンクリートは崩壊し、水は浸入し、鋼鉄が腐食したときに、誰もそれを修復する方法を知らないのです。それはとても危険だと思いませんか?
だからこそ、私たちは建設する過程で知識を共有します。素材はいずれ地面に還っても構わないのです。重要なのは、知識が生き続けることです。社会が変化しても、建物に意味があれば、手入れされながら残っていくでしょう。でも、そうでなければ、いずれ屋根が外れ、壁が崩れて地面に戻っていきます。それで良いんです。
いずれそうなったとしても、その崩れた屋根の上に花の種を植えることができる。それはとても美しいことに思えます。
聞き手:吉澤朋 (文化の翻訳家)

Darko Todorovic/ vai Vorarlberger Architektur Institut