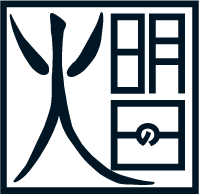2025年8月14日
海辺の美術史
徳田佳世(キュレーター)
アートコレクターであった福武書店(現・ベネッセホールディングス)創業者・福武哲彦氏が1985年に、瀬戸内海に位置する直島の一部を文化エリアとすることを直島町と約束したことからはじまったベネッセアートサイト直島において、担当キュレーターであった美術館が完成した2010年10月、私がキュレーターを担当した豊島美術館が完成した頃、現代アートや建築を生み出す現場にとって、技を持ち、革新を解する職人との出会いが作品のクオリティーに関わると感じ、常に美術や建築の新しい表現の伴奏者として、職人と技を探すことに時間を費やすことが増えてきたこともあり、日本文化を探求する修行に出る決意をし、開館2週間後に京都に引っ越した。
その後、“工芸”に携わる人々と出会い、彼らが情熱を捧げている技と心を理解していくため、私は陶芸について勉強することから始めた。有田、伊万里、唐津、萩、砥部、益子と巡ると、やがて琉球や李朝の歴史が気になり始め、旅や本、映像での勉強を重ねること数年。そんな頃、2016年に発行された『ゲンロン3 脱戦後美術』(東浩紀編、ゲンロンショップ)で朝鮮半島の38度線、DMZ(非武装地帯)でのアートプロジェクトを知り、ソウルから電車、そこからバスで白骨部隊(国防の最前線のため、「白骨になるまで戦う」という意味が込められている)の基地を訪ねた。目の前に広がるのは、果てしない広野。遠くの山頂に北朝鮮の基地が見える。手前には、鉄柵が2つの線を東西に描いている。木々も大地の色も南北で同じに見える。同じ民族だった人々がある日突然、“別々に”なった心情を想像してみるだけで、胸が締め付けられる思いがした。
政治にも経済にも疎い私が情熱を注いできたのは、人が平和や安寧への祈りを込め、その手で作り上げ自然に捧げる“アート”だ。まずはできることからはじめよう。同じ2016年の冬、韓国のアーティスト、ス・ドホからの「アーティストが魂を削って紡ぎ出すアートが作られる状況を生み出すのが君の役割のように思う」という言葉に触発され、建築家の西沢立衛さん、教育者の徳山豊さん、実業家の中田英寿さん、そして恩人である福武總一郎さんの理解を得て、NPO法人TOMORROWを設立した。
大学時代に米国で美術史を学んだ私は、西洋美術史に軸を置いた仕事に就いていた。直島においては、ウォルター・デ・マリアやジェームズ・タレルなど、フランス印象派から美術史の流れを受け継ぐランド・アートの巨匠たちから多くを学ばせてもらった。しかし、地中美術館、豊島美術館いずれの建設にも立ち会った私の目の奥に焼きついた最も強い記憶は、掘削される緑の森が、茶色い土一色になり、コンクリートがドボドボと鉄筋の間に流れ込まれる景色だった。目を閉じると、豊島美術館の建設予定地を最初に訪れたときに見た、青々と生い茂る木々に覆われた湿地帯が思い浮かぶ。
豊島美術館建設前は、その環境を破壊する罪を責任に置き換え、自然を犠牲にする代償として、美しく、感動するアート、そして建築でなければならないと深く胸に刻み、それから完成までの数年間、毎日それを思い起こしながら過ごしたことを今も忘れてはいない。
「美術館は、果たして日本の文化に溶け込んでいるのか?」
このことを疑問に思い始めたのも、ちょうど地中美術館が完成して、豊島美術館を建設するころ。30代で祖父母を亡くしたが、葬儀場で別れを告げ、御影石の墓石の下に骨壷が納められる過程は、美に従事しているはずの自分の職業を疑うきっかけになった。さっきまで私を握りしめてくれていた指がボタンひとつで骨になり、灰になり、しかもそれとてすべてではなく、一部の骨だけが小さな骨壷にぎゅうぎゅうに押し込められ、団地のようにおそろいの墓地に納められる。
墓地のあり方に疑問を持ち続け、タレルから一度は訪れるようにと強く勧められていた奄美群島内の加計呂麻島のとある集落を訪れ、海と祈りの場、生活の場、そして墓地が程よい距離に位置している風景を見たとき、芸術の根源となる“祈り”が暮らしの中にある、古の日本の風景が連想された。
アートが社会で循環するには、人が感動する心を耕せる、集落がある。
そして、兼ねてより考え続けてきた、地球で暮らし続けるとはどのようなことか?空や海や山という、子どもたちが安心して暮らせる地球の美しさを持続させていくために何ができるのだろう?という課題に取り組むために、集落構想「あしたの畑」が生まれた。
ところで、西洋の美術館には、他国に攻め入り、その戦利品を自国へ持ち帰った、凱旋の役目を果たしてしてきたという側面もある。
今も古代ギリシャローマの歴史文化に多くの西洋人が憧れ、誇りを持ち、自らのアイデンティティを裏打ちするための金字塔として、メトロポリタン美術館や大英博物館がある。平和が歴史から学ぶ謙虚な心と教育の賜物であるとすれば、こうした多くの西洋の取り組みはあながち悪手ではない。
一方、私は日本における最古の美術館が正倉院だと考えている。建築的には日本の沿岸部においてよく見られる、収蔵品を湿気や動物たちから守る高床式倉庫で、そこには他国の美術工芸品を愛でる心が感じられる。風土と美術工芸品が、そこで暮らす人と自然に融合していることが日本の美の特質ではないか?
個人の収集を見せる美術館ではなく、そこで作られる芸術文化と食に対する美意識、技術、知識を過去と紡ぎ合わせ、発信することが、これからの世界人――コスモポリタンな心と態度を育む一歩だと思う。
アートにおける精神の伝承には、テキストがあるわけではない。人とのめぐり合いと経験、現場をつくることが、20年先、50年先にも大切にされる、愛されるものを作る責任であり、使命だと感じていた。日本の風土――自然と人との歴史と文化――が世界からリスペクトされる風景を、これからを担う世代の若者たちに委ねながらともに作りたい、それには歴史をもつ土地で、縄文時代を思い起こさせる豊かな自然と人の暮らしの原風景が大切だ。
京都から奈良へ、和歌山へ、三重へ、滋賀へと旅をし、理想の土地を探し求めて、2020年の夏、京都の北、大成古墳群を訪れた。剥き出しの石室、5世紀ぐらいに築造されたものなのだろうか?海に向けてあらあらしく曝け出され組み合わされた石室は、海に向けて死者を弔い、死後の世界を安らかにと願う人の気持ちが伝わってくるような景色だった。
空と海がその祈りを受け入れるかのように、波が岬に押しよせては引く。ここ間人と呼ばれる漁村。アートの大切なものはすべてここにあり、ここから生まれると、ともに訪れた二〇代の橋詰隼弥(現スタッフ)と直感した。
丹後町間人は、京都市内から車で北へ2時間ほどの海辺にある集落。2024年4月、人口戦略会議は、間人を含む京丹後市が2050年までに消滅可能性のある自治体のひとつだと公表した。
岡山にある前方後円墳の周囲が毎日の飼い犬の散歩コースという田舎で育った私にとっては、緑と青と褐色の自然の景色が、想像力を培う栄養であったことを、大人になってから実感した。空き家が目立ち、少子高齢化が進む丹後町の集落が日本各地に見られる状況と重なり、解決すべき課題だと妙な正義感まで抱くようになった。
当初、大学院を卒業したての橋詰とふたりで始めたあしたの畑の活動が、今は、韓国や台湾、香港などアジアからの賛同者とともに、未来につながる教育事業やアートプロジェクトへと広がりつつある。これからの日本、アジア、世界平和のために、祈りを込めて全力で芸術文化活動を行っていく。それがあしたの畑―集落構想であり、その土地のために作られる美術工芸品、建築、そして食の豊かさをもう一度、じっくりと考えること、その過程を次の世代を担う学生たち、そこで暮らす地域の人々と共有することの意義を改めて考えるようになった。
ドナルド・ジャッドのマーファ(テキサス州)、ジェームズ・タレルのローデン・クレーター(アリゾナ州)、ウォルター・デ・マリアのライトニング・フィールド(ニューメキシコ州)、それらはすべてアーティストがこだわり抜いたランドアート作品であることは間違いない。しかし、近年は、環境を破壊し、自然を犠牲にして作られた作品と揶揄する声も聞かれている。
ただし、少なくとも、アーティスト本人を知る私は、彼らがいかに自然を愛し、アートに人生をかけて挑んできたかを知っている。だからこそ彼らの精神を受け継げるような、質において認めてもらえるような作品がうまれる現場を作りたいと考えている。
人やモノ、情報が便利に行き交う時代になると、かえってアーティストたちが1ヶ所に長く滞在して制作することは稀になる。しかし、間人まで来るとなると、それなりの覚悟をもって旅をしてもらうことになる。私たちは日夜、食事を共にし、考えを交換しながら、それぞれプロとしての仕事を全うしようとする気持ちになる。毎回、ひとりひとりと真剣に向き合うので、大変なエネルギーを消費する。国が異なると抱える認識や知識が違う。それらを理解しようとしながら、興味を持ち、できるだけ楽しんで、遊ぶように作品を作ってもらいたいと思っている。
そうしないと、人の心を揺さぶる作品は、できない。
食に、アートに、工芸に、建築にと、ひろげるだけひろげてしまった風呂敷の大きさに、なんということをしてしまったのかと頭を抱えることもある。知識も資金も追いつかないことに呆れながらも、知らないことを知る、どうにかするためにまた本を読み、人に会い、考えて、行動に起こす、その連続だ。
今や多くの人々が訪れる、直島を拠点とする瀬戸内の賑わいも、着手から40年を迎えようとしている。丹後における「あしたの畑」でも、50年後、100年後の人々の誇りとなる遺産を生み出していきたい。
私の望みは、間人での取り組みがいずれ日本の美しい海辺のアート集落モデルとなり、世界各地から訪れる場所、学生にとっては学びの場へと育つことだ。そして、美が人の心を救い、子どもたちが、すべての生命が、平和に生きる世になること。
アートがどんなにがんばっても、もう間に合わないかもしれない。しかし、地球は、自然は、あまりにも強く、そして美しい。アートを通して自分の心に向き合い、限られた人生の中での自分の生き方を考える時間を持つ大切さを感じて欲しい。そんな体験型の暮らしのアートが世界中に存在していることに気づくきっかけになるぐらい、美しいプロジェクトにしていきたい。
徳田佳世、2024
その他のコラムはこちら