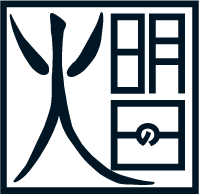2024年10月2日
あしたを耕す者たち
第2回
徳田佳世×中川周士
あしたの畑のものづくり
京丹後市・間人(たいざ)を拠点に展開される「あしたの畑」に開始当初から関わっている木桶職人の中川周士さん。作品として造るものはいつの間にか手で持つ木桶から、人が入ることのできる茶室まで幅が広がっていた。
NPO法人TOMORROW代表の徳田佳世さんとの出会いは、徳田さんが京都へ移住した2010年。工芸をより深く理解する為に移住した徳田さんと、京都一の木桶職人と称えられた祖父を持つ中川さん。二人が出会い、始まった共同作業から生まれ続けるのは、「もの」にとどまらない。TOMORROW事務局橋詰隼弥さん同席のもとお話を伺った。
第一回のインタビューで徳田さんが2㎜の違いを気にされていた地中美術館建設時代から、今では20㎝の違いに口を出さなくなったというエピソードが印象的でした。中川さんは、その「2㎜にこだわる時代」からのお付き合いですよね?
徳田佳世(以降T):
現代アートの作品をつくるのに何人もの職人さんの卓越した技術が必要なんだ、って気づかされた後に京都に来たんです。同じ素晴らしい技術でも木桶のシャンパンクーラーだったら7~8万円で、かたや現代アートの作品になったら数千万円という違いはなんだろう?と不思議に思って、まず工芸の世界の仕組みを徐々に学んでいるところでした。
中川さんとは比較的すぐに知り合いましたよね?
中川周士(以降N):はい。当初は、まず徳田さんから依頼を受けたら、どうやってそのイメージを実現しようかっていうスタンスで作品に取り組んでましたね。徳田さんの反応をみながら。
どのように作品作りを進めるんですか?
N:杉本博司さんとのコラボレーションがいい例なんやけど。杉本さんの方が優しいというか、受け入れる許容度があったのに、徳田さんがなぜか横から「ダメ」って言うんですよ。「お前の作品やないやろ」って思ったんですけど(笑)。
まず杉本さんからもらった図面があって、まさにそれ通り、ミリも違わずきっちり仕上げたんですけど、「違う」と。始めは全然意味が分かりませんでしたね。クライアントからの注文通り作るっていうのが職人の仕事で、矜持でもあり。でもそれが違うって言われて。
T:「でも違うものは違う」って。
N:「それって、自分のものになってなかったからなんだな」と後から気づいて。もう一度自分の中で解釈し直して、消化し直して出てきたものには、杉本さんも徳田さんもオッケーだしてくれて。
T:「なんで最初からこれつくらなかったの?」 てね(笑)
N:他人の褌というか…誰かの指示に合わせて作ったものにはどこか甘えがあって、それを見抜かれるんだな、と。そこを見抜く感性というか、感覚っていうのはやっぱり徳田さん独特だなって思いますね。

徳田さんは提出された作品の、どこをご覧になっているんですか?
T:かっこいいかどうか。迷いがないかどうか。
箱を開ける前に、もう梱包の仕方である程度伝わっている気がしますね。自信があるときは、すごくきれいにびしっと収まっているし。これさっきまで微調整してたんだなって伝わってくるような、蓋から包み布がはみ出ているようなときは、「なんで今日持ってきたの?」って、そのまま見ないこともありましたね。
N:コンセプトを壊しちゃうのが徳田さんなんですよ。例えば僕らコンセプトから作品作りする時は、テーマがこうだから、とか、場所がここだから、とか、順序立てて階段一段ずつ踏んで、まあ因果関係みたいなのを感じられるものになるんだけど、その因果関係とか積み重ねをつぶしちゃうのが徳田さん。
最初から積み上げてきたものをがらがらつぶすような、全然違うところのものをポンと放りこんでくる。で、それまでが全部ひっくり返るんですけども。でもそういう時って、実は全体が違った方向に向かっている時なんです。そんな中に、なんか予言めいたものを放り込んでくる。
(橋詰)徳田さんに「こう言いましたよね?」っていうのはだめなんです。言葉とは違う論理から来ていて。もともとコンセプトの奥底にあったものは変わっていないし繋がっていて、むしろコンセプトが違ってきていた、っていう。
N:一番深層のところはずっと変わってないんだよね。
言葉とか論理を超えた部分に直感的につながっているのですね。
N:徳田さんのすごいなと思うところは、本当はこれがつくりたかったものなんだっていうことを気づかせてくれるんです。
階段登ってると、その階段登ること自体が目的になることがある。階段登ること自体に達成感というのはあるんで、ものづくりっていうのはそれでいいんやけど。でも本当に作りたいものは、それらの流れに抗って自分で考えなきゃ生まれなくて。徳田さんはそこを求めてる。
T:だってみんな死ぬでしょ?死ぬまでにいいものつくりたいですよね。
だからいつも「何つくりたいの?」って最初に聞きますよね。
本人さえも気づいていなかったつくりたいものが生まれる過程は、壮絶でもありますね。
N:杉本さんとのコラボ作品を展示しにロンドンに行った時に、照明に駄目出しをされたことがあったよね。杉本さんが翌日来る予定で、その前に徳田さんのチェックが入って「照明が美しくない」と。「杉本さんが来る明日の午前中までになんとかしなさい」って言われて。
僕英語しゃべれないじゃないですか?でも街中の電気屋さん回ってあらゆるLED電球を買いまくって。とにかく「More,More」って(笑)。全部で40個くらい買ってきて、梯子登って付け替えたんですけど、どの電球もダメで。
LED電球って、光量をアップするために小さいLEDがいっぱい付いていて、それらがお互い干渉しあった影が美しくないっていうことに気づいたんで、LEDを分解してその数を減らすっていう作業をホテルに戻ってからして…次の日の朝、ようやくOKでましたね。
T:でもそうしたらね、結構いいコレクターが買ってくれて。それできちんとまとまった報酬も渡せましたよね。
N:徳田さんとの仕事っていうのは、徳田さんが納得するまで何度でも試作したり、職人としてもその間は収入にならないので、それを耐え切れずに辞めていった人もいるし。 でも僕は単純にお金だけじゃなくて、なんか「この人の頭の中を覗いてみたいな」っていう思いがあって、諦めなかったですね。

中川さん作の飼い葉桶についても教えて下さい。
T:その頃、「七人の侍」を見直してたんですよ。そしたら馬が大きな桶の中にある牧草を食んでいるシーンがあって、それ見て「かっこいいなあ」と思って。「これ作れる?」って、また写真を送って。
N:あれは、大変でしたね。一回目の試作からはコロッと変わりましたね。一回目は馬にかけられるように縄を使っていたんですけど。見てもくれなかった(笑)。
T:「なに?江戸時代再現したの?」って(笑)。あしたの畑の象徴となる作品を中川さんに創ってほしい、と思っていたから。
N:僕も「あ~これじゃなかったのか」くらいで、もうそこまで気にせず、次の事を考えて。そこで飼い葉桶っていう用途、つまり目的を考えずに、桶の直径と高さのバランスとか、箍のバランスとかを改めて考えて。純粋に美しい桶と思えるものを作って提出したんですよ。
それはめでたくあしたの畑に入れてもらえて。工房でできあがった時よりも、田んぼの脇に置かれたのを見た瞬間に腹落ちする部分があって。「あ、稲穂を入れる桶やったんや」と、はっとしました。

T:これを見て、中川さんは建築物も作れると思いました。この上辺の仕上げが斜めになっている部分、そこを見て。私が特別指定したわけではないけれど、こういう仕上げで出してくれたことに。それ以降あまり注文つけなくなりましたね。
N:これは、うちのじいちゃんから教わった木桶の仕上げ方で。その角度の付け方がやっぱり美しいと思ってたんで。ちょっとだけ見せた僕の個性なんですよ
T:「わぁ、中川さんと大きなスケールのものが作れる」って嬉しかったですね。私一人じゃ本当に何もつくれないから。みんなでしないと楽しくないし、いい作品にもならないし、幸せにもなれない。その象徴的なものとして、あの飼い葉桶があるんです。
皆でつくるっていうのは徳田さんのキーワードですよね。
T:素晴らしい作品って、その空間に入った瞬間や思考している時に音が聞こえるような気がして。例えば建築家の西沢立衛さんは、豊島美術館建設中の現場へ向かうフェリーに乗るとザ・ローリングストーンズの「ジャンピン・ジャック フラッシュ」が聴こえると仰って。私にはチェリストのアンナー・ビルスマが奏でるベートーベンが聴こえてきましたし。そういうふうに、空間に入ったときにインスパイアされる音楽を自然と感じるような時はうまくいってるんです。言葉にはできない調和みたいなのがあって。そこにあるディテールすべてで奏でている協奏曲が感じ取れるとき。
N:あしたの畑って言い始めてから、ようやくその徳田さんの本当にやりたいことが少し分かったような気にはなってます。

T:中川さんに間人スタジオに作ってもらった机には、もう何も言わなかったよね。
N:明後日にメディアが来るから、明日中に搬入しなきゃいけないってときで。でもトラックに積み込もうとした時に、これは違うと思った。それで、一旦降ろして、そこから表面全部削ったんです。
最初は、つるっとした仕上げで、それだと陰影が出ないけど、表面を鉋で削って凹凸をつけたら、陰影が現れる。あしたの畑のテーブルはこれしかないって思い込んで、ひたすら畳二枚分の机の表面を6時間かけて削り直した。

その頃には自分のつくるものが自分のものになってたんですね。やらされてるとか、手伝ってるとかじゃなくて、自分ごとになった。そうするとね、徳田さんから言われたことも、その言葉の裏にあるメッセージが聞こえるようになったっていう感じ。
T: それを見て、あしたの畑は私だけのものじゃない、みんなでつくってるっていう実感がもてました。
聞き手:吉澤朋(文化の翻訳家)