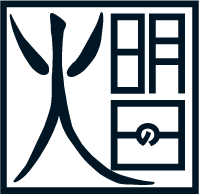2021年6月10日
「食べることと食べられること」
藤原辰史(歴史学者)
私たちは、あるものを食べることができる。しかし、私たちは、あるものによって食べられることもできる。生命活動を終えたあと、土葬や鳥葬すれば、私たちは土壌に棲む無数の生物や空を飛ぶ無数の鳥たちの食べものになることができる。もちろん、こういったことを美しい自然物語として語りたいのではない。第二次世界大戦末期、現在のミャンマーで、日本軍と英軍が戦ったインパール作戦では、司令部の無謀な作戦で戦死したり、餓死したりした若い兵士たちがそのままジャングルに残され、高温多湿多雨の気候ゆえに、すぐに白骨化した。そこは「白骨街道」と呼ばれたが、遺体の分解プロセスは、無数の生きものの作用がなければありえないことである。本来は、家族や仲間によって丁重に埋葬されず、国家によって遺棄された遺体であっても、生きものは容赦なく死者を襲うのである。
たとえ死に至る前であっても私たちはすでに食べものである。生態学者のロブ・ダンの著作『家は生態系Never Home Alone』によると、どんな人でも一日に5000万個くらいの皮膚の断片を床に落とす。そして空中をふわふわと漂うその断片ひとつひとつに、数千もの細菌が棲んでいて、それを食べている、という。もちろん、私たちから抜け落ちる体毛も床のダニや細菌の立派な食べものである。ロブ・ダンによれば20万種類の生きものと私たちは一緒に暮らしているらしい。
私たちの分泌物も食べものである。皮膚の汗は常在菌の食べものであるし、排泄物は腸内細菌の食べものであることはよく知られているとおりである。それらとの共存関係によって人間が免疫機能を有効に働かすことができることも、最近、しばしば指摘されるようになった。
私たち人間だけが、捕食されることから免れた生きものではない。もしも、ワニやトラやクマやサメが生活環境の近くに棲んでいれば、いつそれらの生きものに食べられてもおかしくない。
いつ食べられてもおかしくない存在として自分を考えること。死んだあとでも自然の生きものたちにとって、おいしい食べものとして生きること。そんな目標を持って生きている人はもちろん、意識して暮らしている人はほとんどいないだろう。私たちは死んだ後も火葬になり、大量のダイオキシンを排出しながら、骨と灰になって、骨壷に入れられ、土壌と遮断される可能性が高いから、自分が食べものであるという考えには馴染みにくい。
生態学者のハインリッチは、著書の『生から死へ、死から生へLife Everlasting』で、自然葬を望む重病の同僚との手紙を紹介しながら、本来、死は「再生を祝う野生の祝賀会a wild celebration of renewal」であるのだと述べ、火葬による商業的葬儀がそこから逸脱している、と批判している。私の島根の田舎の実家は曽祖父と曽祖母までは土葬であった。田んぼに囲まれた丘にある墓地で多くの先祖たちが土壌内生物たちのご馳走になり、それが周囲の木の構成要素になっている。人間が食べるとはどういうことかという問いにはいつも、人間が食べられるとはどういうことか、という問いが表裏一体となっていなければならない。