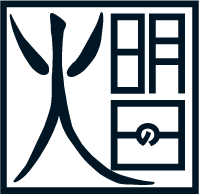2024年8月26日
あしたを耕す者たち
第⼀回
徳⽥佳世
⼈の⼀⽣を超えて完成する世界に⽬を向け続ける
2024年に4年⽬を迎える「あしたの畑」。京丹後の間⼈(たいざ)を拠点に集落構想を展開している。有機的な広がりを⾒せる「あしたの畑」の活動を貫く軸について伺うため、発起⼈でありNPO法⼈TOMORROWの理事⻑である徳⽥佳世さんをSEI KYOTOに訪ねた。 事務局の橋詰隼弥さん、中川⽊⼯芸の中川周⼠さんから時折⼊る合いの⼿に助けられながら進められたインタビューでは、徳⽥さんの来し⽅、そして⾒つめる未来を紐解く。
地中美術館(2004 年開館)、豊島美術館(2010 年開館)と、瀬⼾内海を⽇本における現代アートの巡礼地とする⼀連のプロジェクトに中⼼となって携わったのち、京都に移住し、職⼈、⼯芸作家、アーティストと協同でものづくりに取り組むようになりました。傍⽬には急激な⽅向転換です。
よく聞かれましたね。「アート辞めちゃうんだ」って。私としてはずっと、アートというか、 私の興味を追ってきただけなので、きょとんとしてしまいましたが。 ずっと、36歳ぐらいで死ぬのがベストと思ってたんですよ。36歳位までに何かできてないといけないなあ、と。でも「あれ?なんか37歳でも⽣きてる」と気づいて。そしたら次を考えざるを得なくなったというか。
それまではまだ次があるという意識で仕事していたんです。次のプロジェクトや出会いや…でも⼈⽣で美術館建設ってそうたくさんあるものじゃないんだな、とも気づいて(笑)。
じゃあ、争いのない世の中にするために、芸術で何ができるんだろう?て。従来の美術館ではやっていけないという思いもあって。⾃分の事として、これからの美術館をつくるとしたらどうなるんだろう、と考えるようになったんですよね。
あと、なんとなくもう来世はないな、という気がしているんですよ。ここまで⽣きてきて。 もうこの世には戻ってこないな、と。となると、⾃分がどうこうというよりも、いずれ⾃分がいなくなる世界を、⾃分で新たに作っていくと考えた時に…次の世代のことが気になりだしたんですよね。
これからの美術館の在り⽅に⽬を向けるようになった?
美術って、五感に栄養を与えるものですよね。芸術体験を通して⾃分の頭で考える機会を提供する教育の場でもあるはず。売っているもの、触れるもの、⼝にするもの、全てが総合的に感性に働きかけるような体験であってほしいと思っていて。その場所にいるからこそ感じられる感覚を得てほしい。どこにいても同じ、ではなく。
課題として、観賞料収⼊だけではやっていけない美術館の事情もよく分かってたんです。「どうやったら社会の中で美術・芸術が循環し続けていけるんだろう」という問いに対する答えは、⾃分⾃⾝が崖っぷちに⾝をさらさないと⾒つからない、と感じたんですよね。
それで京都の町屋を改修して、そこに住んで。ここに住み続けることはその問いに向き合い続けることでもあるんです。

SEI KYOTO
SEI KYOTOを拠点に京都の⼯芸との交流が始まります。なぜ京都なんですか?
30 代になって、ひとつの現代アート作品を作り出すのに、様々な分野の職⼈が多数携わっていることに⽬線が向くようになって。その⼀⼈ひとりの存在をはっきりと認識するようになったんです。それぞれの仕事の痕跡を記憶に残したい、と。そのためには⽇本⽂化をもっと理解する必要があると感じるようになりました。
もうひとつは、「やっぱりいいものじゃないと感動しない」という確信もあって。⼿の技術のある、優れた作り⼿でないと、この国に良い美術は残せないと思って。当時の私は、「せっかく⽇本にいるんなら、やっぱ⽂化って京都じゃない?」みたいな(笑)ある意味帰国⼦⼥みたいな感覚で京都を選びました。
そこで、職⼈や⼯芸作家、アーティストらと⼀緒にアート作品の制作に取り組まれた。
でも今思うと、その原点は地中美術館建設の時にあって。
例えばモネの作品展⽰で、2m×6mの作品を幅10mの壁に展示するとき。私は作品から20m引いたところから見ていて、片方が2mm下がっているのが見えるんです。それが気になるんですけど、その頃私はまだ30〜31 歳ぐらい。周りの職⼈さんはほとんど年上のなか、その2 ㎜が気になる感覚を共有できるようになりたくて。その為には「職⼈さん全員と気持ちが⼀緒にならないと良いものは作れない」と。
アートだけ良くても、そこに⾄る道とか、周りの環境のせいで意識が逸れちゃったら感動なんかできないと思うんです。その環境づくりのためには、建設に携わる⼈全員と気持ちをひとつにしないと…その関係を⼀年半ぐらいかけて作っていったのです。
それは毎⽇みんなでラジオ体操することから始まって、お昼ご飯も⼀緒にお弁当を⾷べて、現場でも⼀緒にヘルメット被って。現場にいる⼈全員の名前と個性、家族構成も全部理解して。
休みの⽇も、朝から駅前に集合して、みんなでバスに乗って何か⾒に⾏くとか…。⼀⽇中⼀緒に過ごして、⼀緒に⾷べて、感想を⾔い合って。職⼈さんそれぞれで⾒るところが違うじゃないですか?その視点を学んでいく。そして私の話もすると、彼らにとってのアートも、 ただの訳わかんないものではなくなっていくんですよね。⾃分の照明、⾃分の設備、⾃分の技術が、この美術館という作品を作るんだっていう意識に変わっていく。そうすると⼀つのゴールに向かっていけるようになるんですよね。
例えば、天井にはめる間接照明。円形だったら、リング状になっていて、どこかに切れ⽬があるんです。私は、その切れ⽬が全部同じ⽅向を向いてないと気になってしまう。でも普通 は、そこまで⾔わないんですよね。「ちょっとここずれてるよ」なんて。でも、その頃は関係性ができていたから、パッと空間に⼊って、天井⾒た瞬間に、何も⾔わなくても「すぐ直します」って設備屋さんが⾔ってくれるくらいのチームになってたんです。
その時とほとんど同じチームで豊島美術館は建設されています。むしろ同じ職⼈さん達でないと無理だったと思うのです。技術的にも、左官の仕上げとか。地中美術館があったから、豊島美術館がある、と。
職⼈といいものをつくる、っていう仕事をさせてもらって。あの時に私⽢やかされたんだな、って思いますね。逆に既製品だけではいいものはつくれない、っていうのも実感して。
その経験をして、そのまま京都に来ちゃった。

改修前の間人スタジオ2階にて、嘉戸浩氏(かみ添)と中川周士氏と
地中美術館で1 年半かけて⼼をひとつにしてきたプロセスを、⼯芸の分野でどのように再現しているのですか?
(中川さん) 写真が⼀枚だけぽんっと送られてくるよね。「これで何を⾔おうとしてるのかな?」と考えさせる(笑)
こう、作品だけ⾒て⾊々⾔うと個⼈攻撃になっちゃう。「ここがこう違う」って、専⾨でもないのにどうでもいい突っ込みしだしたら⾃分もつまんないし、世界を共有できない気がして。
それよりも、「ここへ⾏きたいんだよね。」「次はこの美の世界を⾒たいんだよね。」「⼀緒に作りたいんだけど、どうすればいいの?」っていうのを、⾔葉じゃなくて、⽂学とか⾃然の中に⾒つけた⾃分の答えを⾒せる中で共有したくて。それで写真送っちゃうのでしょうね。
今も当時も変わらず、⼀緒に⾷べてお茶して。本や旅⾏や体験を通して、世界を共有する、と⾔う⽅法ですね。「この世界を⾒たいんだよね」って視線が合うようになると、そのうち違和感も共有できるようになるし。やっぱりみんなでつくるスタイルが好きだから。

韓国への視察。新里明士氏と杉山早陽子氏(御菓子丸)と
地中美術館をつくっていた頃から変わったことはありますか?
当時は2㎜下がってるのが気になったけど、今ね、20cm違うんですよ(笑)。だけど⾔わない。 ⾔わないようにしてます。 だってもう世代が違うじゃない?普通にいけば私の⽅が早く死ぬから。彼らが次の世界をつ くるんだから、私が⾔っちゃいけないって思うようになりましたね。
求めているものが変わったんですね。2mm にこだわって⾒せたい世界と、20cm に⽬をつぶってても、それが決して妥協ではなくて、また別のありたい姿というか。
なんかMy WorldがOur Worldになった感覚です。
アートは社会の縮図だと思っていて。そのアートの世界で、⼥性である私の世界観にはどういう意味があるんだろう、って時々考えますね。⼯芸って⾔ったら男⼦、⼿芸だったら⼥⼦、 とか。組織となるとトップは男性っていう社会で。直島にいた頃も、現場で⼥性を⾒かけることはほぼ無い状態でした。私がズカズカ⾔っても、軽くあしらわれたりする。なんかメッセンジャーぐらいの扱いで。そこから私の意⾒を聞いてもらおうとしたら、凄まじい努⼒をしなきゃいけなかったわけで。今でもこのNPO法⼈で私の上⻑は誰ですか?ってよく聞かれますしね。
卑弥呼にしろ持統天皇にしろ、⽇本の歴史を辿ると男⼥が平等だった国のはずで。まあ男⼦が政治をして⼥⼦が巫⼥るみたいな役割分担はあるかもしれないけど、もうちょっとお互いのことをリスペクトする関係があったのでは?と不思議に思いますよね。
私は⼦供がいないので、⼥⼦に⽣まれたのに…という申し訳なさを仕事で補填しているのでは、と時に感じることもあるのですが。じゃあ⼥性だからこそ何ができるだろうっていう問いへのヒントは、芸術の役割とか、⼥性性の中にある気がしますね。
例えば建築物はなんで⼤きくなきゃいけないの?とか。⼤きな社殿が修復できない、っていう時に、私は、「そしたらもう⼩さな祠でも」と思うんだけど、「このサイズじゃないとだめなんだ」っていう考えとか。プライドなのか…そういうのはちょっと男性性っぽい気がして。そこをもっと無理せず⾃然とつながっていけば、この島国で豊かな⼼で⽣きられるんじゃないかって。
(中川さん)⽯が三つ積んであるだけで、思わず⼿を合わせたくなる感覚はあるもんね。
それでいいんじゃないかと思う時は確かにありますよね。神社だって、もとは湧き⽔が出ていたから、とか、そういう始まりなのに、どんどん上物が⼤きくなって、ちょっと権威主義みたいになっちゃったり。

沖縄への視察。Teresita Fernàndezと娘のCypressと
いま、間⼈という集落にあしたの畑の世界が展開されつつありますね。
ハコの中にない美術館だと思っています。
当初から「集落」ということにも興味があって、直島にいる時も図書館とか集会所みたいなものが作りたかったのです。地域の⼈とアーティスト、詩⼈とか、科学者とか、様々な分野に関わる⼈が訪れるなかで交流をして、世界について考えるような場を作りたかった。
美術館ではあるのだけど、アートだけに限るとか、詩⼈の場所をつくって詩⼈に来てもらうとか、そういう限定的な感じじゃなくて。
環境に対してこういうことを考えてるから、こういう⾷を提案しますとか、こういう器によそいますとか。そういうものを⽣活に取りこんでほしいから。アートも含めて、そういう体験を共有することで⽬指す世界を伝えたいですね。
あしたの畑は、今後の美術はこうあったらいいなっていう世界を表現しているんです。もう美術館もないし、⼤学もない、ほとんどの⼈がアートにふれたことのない京丹後市・間⼈でアートをしよう、ってなったとき。「正倉院を越えられないんだったら美術館を作っちゃダメ」って、思ったんです。何かを建てる、あるいはつくるということは、そこにあった環境や生態系に影響を与えることで。それでも何世紀か経ったあとにその価値が残って、豊かな世界の一端を担えていれば。最大の志ですね。
アートの在り⽅、関わり⽅、新しい美術館のありかたを探りながら同時に提案していくのが あしたの畑でしょうか?
⼀年⽬はあしたの畑ってなにやってるんですか?って訊かれてもうまく説明できなかったけど、ようやくかたちを⾒てもらえるようになりましたね。
やっぱり⾔葉や写真で伝えるだけじゃなくて、間⼈に来てもらうしかない、というか。
(橋詰さん)後から分かったんですけど、間⼈は東京から⼀番遠い場所なんですよ。公共交通機関で7〜8時間っていう。沖縄よりある意味遠い(笑) だからこそ、⽇帰りじゃなくて、滞在してもらって、体験してもらえる。
あしたの畑は⽣きている間には完成しない、と書かれていましたが…
あしたの畑は完成しない。完成しない⽅がヘルシーだと思います。
とはいえ、⾒届けて死にたい気持ちもありますね(笑)
聞き手:吉澤朋(文化の翻訳家)
その他のコラムはこちら

2021年9月30日 間人スタジオ竣工式